 |

 |
|
 |
 |
 |
 |
| 優秀賞 |
 |
|
 |
(1)
結婚して三十五年も経った。十年一昔と言うなら、三十年以上は大昔だ。そんな長き歳月を、本当に納得できるような生き方をしてきたのだろうかと、初老になったこの頃しきりに考える。
少女の頃、私も多くの夢を持っていた。まず教師、そして看護婦、それから婦人警官、保母、宣教師、画家、占い師、女優…。
それらはその時々で変わる、今にして思えば動機も実にたわいないものであったが、運と努力次第で手中にできると確信していた。
だが、結局のところ私はそれらのどれになることもなく、一人の男性の妻になった。
結婚後の彼は、仕事に情熱を傾け、家庭ではよき夫と父親だった。
私は二人の息子に恵まれ、家事と育児で日を送る充実した毎日だった。幸せを絵に描いた、という表現はこんな私を言うのだろうと自負していた。だがそれは永遠ではなかった。
やがて、成長した長男が学校を卒業して家を離れ、次男も続いた。夫は出世して出張と帰宅の遅い日々が平素のこととなった。何もすることのなくなった私だけが独りぽつんと家に取り残されていた。
悶々と考える日々が続いた。私の人生はなんだったのだろう。ただ夫や子供たちの世話に明け暮れるだけのものだったのか。これからは何を生きがいにしていけばいいのだろう。私に何かできることがあるのだろうか。
納得できる答えを見出せぬまま鬱々と眠れぬ夜を幾晩も過ごしたあと、遠い地へ旅をしてみようか、との思いが脳裏をよぎった。どこへ? そうだ、以前ツアーで行ったことのあるインドへ出かけてみよう。
あの時は、一週間を朝から晩までひたすら観光地巡りで終えたが、今回は同じ所でゆったりと過ごしてみるのはどうだろう。インドのどこにしようか? いやいや、考えるまでもない。ガンジス河しかないではないか。
早朝のあの時、眠い目をこすりながらまだ明けやらぬ河岸で、黒い肌を持つおびただしい数の老若男女の沐浴をあわただしく見物し終え、いつか機会が訪れたならゆっくりとここで過ごしたいものだと思ったが、今がその機会であるに違いない。
そう決めると矢も立てもたまらなくなり、私は即座に旅の準備に取りかかった。
(2)
インディラ ガーンディー国際空港に到着したのは深夜だった。十月だというのに夏並みの暑さだ。
リュックに入れていた扇子を取り出し、ばたばたと扇ぎながらターンテーブルから出てきたスーツケースを降ろし、フーッと大きな安堵の息を吐いた。辺りには懐かしい香辛料の匂いが漂っている。とうとう三年ぶりのインドに着いたのだ。 出口の自動ドアが開くと、通路の両脇の鉄パイプの外側に大勢の迎え人が溢れかえっていた。ほとんどが男性だ。皆一様に色が黒く、僅かな灯りに反射して時おり目が赤く光る。
見廻すと「ミセス ウメキ」と、茶色の馬糞紙一面に大きく名前を書いたものを、両手で高々と頭上に掲げた髭面の大男が目に入った。彼が、今夜一晩だけ利用するホテルの従業員だ。電話で頼んだ甲斐あってちゃんと迎えに来てくれている。
「ナマステー」
片手を挙げて挨拶の言葉をかけると、私に気付いた彼は人ごみをかき分け、真っ白な歯を見せて大股で近付いてきた。
翌日、デリー駅二十二時発の列車に乗車し、十七時間後の十五時、ムガル サラーイ駅に降り立った。
スーツケースをホームへ降ろすが早いか、あっという間に屈強そうな数人のポーターに取り囲まれた。自分の客にしようと、口から泡を飛ばして口々に金額を競い合っている。
私はそんな彼らの様子をひとしきり眺めたあと、歳はかなりいってはいるが、温厚なまなざしの男を指名した。
彼は、慣れた手つきで持っていた布切れをくるくると頭に巻いて当て布にすると、その上に私のスーツケースを軽々と載せ、見失わずに付いてきているかどうかと何度も振り返りながら混雑を極めるホーム内を進みだした。
駅の待合室は、見渡す限り列車待ちをしている雲霞の如き人、人、人で埋まっていた。
華やかなサリーを纏い、多くの煌びやかな貴金属で全身を飾り立てている上流階級の夫人。
豊かな経済力を誇示するかのような太鼓腹を突き出した丸い眼鏡の男性。
小さな頭髪をきちんと七、三に分けられ、行儀良く座っている育ちのよさそうな男児。
シーク教徒であることを示している白いターバンの大男。
全身を黒一色で包み、描いたかのような美しい眉と情熱的な黒い瞳を持つエキゾチックなムスリムの女性たち。
針金細工の小さな玩具で遊びに熱中している子供たち。
無心に編み棒を動かす若い母親。
聖者のように威厳すら感じさせながら我が物顔で徘徊する白い瘤牛。それらの間を縫うようにしながら、錆びたブリキ缶をだれかれなしに突き出す足の皮が靴底のように分厚い物乞いの老婆。
人や動物や食べものや汚物といった様々な臭いが混ざり合い噎せ返る熱気と騒音の中で、人々は思い思いに時間を過ごしている。ある人はのんびりと、別の人は命がけで、悠久の昔から変わらぬ時間を過ごしていた。
(3)
ホテルのルームサービスで朝食を済ますと、Tシャツにスパッツ、リュックに帽子という軽装でホテルの玄関を一歩出た。ガンジス河にいざ出発というわけである。ところが、
「何なんだ! これは」 |
| 眼前の光景は、思わず声に出るほどの凄まじさだった。バス、タクシー、乗用車、サイクルリクシャー、オートリクシャー、リヤカー、自転車、といった車輪の付いたありとあらゆる乗り物が、信号もない大通りを埃を舞い上げながらやたらとスピードを上げて走行していた。 |
 |
 |
どうしたものかとしばらく眺めていたが、とにかく行くしかない。私は車の切れ間を待って向こう側へ渡ろうと試みた。だが、あまりに道路幅が広く一向にそのチャンスが来ない。まごまごしていると、真っ黒に日に焼けた(日に焼けなくても元々が黒いのだが)若者が走り寄り、私に任せなさいとばかりに手を掴み、走る車をものともせず片手を挙げながらすいすいと進んでいった。
なるほど、コツが分かった。車を意識するのではなく、車に意識させればいいのだ。
さて、ここからガンジス河は…。方向を確かめると、そちらに向かって歩き始めた。
「ガンガー?」
一人の年配の男が、サイクルリクシャーを引っ張りながら、声をかけてきた。
この車と人の洪水だ。ガンガー(ガンジス河)まで優雅に散歩ってわけにはいきそうにない。どうやら、善良そうな顔をしたこの男のリクシャーに乗るほうが賢明らしい。
彼は器用に、左右を突っ走る車との接触を避けて運転しながら、十分程で細々とした土産物屋が軒を連ねている辺りで停車した。 |
前方に目をやると、ガンガーが、建物の間から陽光を浴びてきらきらとした美しい水面を見せて私を迎えてくれた。
一般に沐浴は陽の出と共に行われる。したがって、陽が高々と昇ったこの時間帯に河に浸かっている人はさほど多くない。だが、小舟に乗ったり、周辺を散策したりしている観光客の数はかなり多い。
|
 |
 |
 |
 |
ガート(沐浴場)の階段に腰を下ろし、頬杖をついて辺りを眺めていると「安くしておくからボートに載ってくれない?」変声期前の甲高い少年の声が頭上からした。
「幾ら?」と尋ねると「百ルピー」と打診するような表情で返事が返ってきた。
|
日本円で三百円は高い。以前乗った時は一人五十ルピーだったと記憶している。駄目元で「五十ルピーでよければ」と言ってみると、少年は意外にも即座に「オーケー」と応じた。
岸辺に括り付けられている多くの舟の中でしばらく悪戦苦闘した後、年季の入った少年の舟はようやくそれらから離れ、河面を滑るように進み始めた。
頬を撫でる微風が心地よい。
目を閉じ、ゆっくりと聖河に浸かって瞑想に耽る老婦人。
神妙な顔で献花を流している娘たち。
大きな壷に聖水を汲みいれている品の良い紳士。
肋骨が標本のようにくっきりと浮き出たドーティ(腰布)一枚の老人が、よたよたとおぼつかない足取りで河に入ろうとしている。
歯を磨き、水を口に含み、顔を洗い、次いで全身を石鹸の泡で真っ白にして洗い始めた毛深い男。
その隣は、客から預かった洗濯物を石に叩きつけるようにしながら中腰になって洗っている洗濯屋の一団。
彼らの上方には、ガイドブックにもお馴染みのホテル群や、三角屋根のどぎつい色の寺院が櫛比している。
火葬場の煙突が見えてきた。死人を焼いている白煙が中天に向かって昇っていく。
「観光で来たの?」少年が、客にいつも尋ねているであろう月並みな言葉を口にした。
肯き、今度はこちらが質問する番だと私もやはり月並みに「幾つ?」と聴いてみた。
少年は十三と答えると、貴女が聴きたがっていることはよく分かっている、とでも言うように分別顔で話し始めた。
自分は長男で、下に弟と妹が五人いる。一番下の妹が生まれる前の月、父親が事故でなくなってしまった。母親は働けず、当然の如く自分が一家を背負う立場になった。形見となったボートで父親がしていたこの仕事を始めてみたが、この頃ようやく何とか食べていけるようになった、と。
「貴方の夢は?」
「弟たちを一人前にして、妹たちの花嫁料を作って嫁がせて、家を建てて、母さんを安心させてあげたい」
私はどう返事すべきか、迷っていた。立派ね。日本の子どもたちに貴方の爪の垢を煎じて飲ませたいわ。お母さんも貴方がいてくれて幸せね。だが、何も言えなかった。自分自身の方向が見出せずもがいている今、いろいろな言葉が胸中を去来しただけだった
「向こう岸へも行ってみますか?」
少年は私の気持ちを察したのか答えを待たず、不浄といわれている対岸へと舳先を向けた。まだ骨も筋肉も柔らかな体ではあったが、艪を握る腕は微動だにしていなかった。
(4)
ホテル前の車が行きかう道路わきには、砂埃を浴びて真っ白になりながら、果物や八百屋の露天商がずらりと並んでいる。
それらを眺めながら、友人に便りを出すためポストカードを買って来ようと歩き出した私に、親しそうな声がした。振り向くと、先日、道路を横切れない私の手を引いてくれた若者だ。彼は八百屋さんだったのだ。
「何か買ってよ。安くしておくから」と泥の付いた野菜を指差した。
隣店の少女も笑いながら大声を張り上げた。「うちの人参も大根もジャガイモも、そっちより美味しいし値段も安い。こっちで買ったほうが得だよ」
私もユーモアで返した。「日本へ帰るときのお土産にしようかな」と。
十枚ばかりのポストカードを手にした私をどこで見ていたのか、この前乗ったリクシャーの運転手が近寄り「今日はどこかへ出かける予定はありませんか」と礼儀正しく聴いた。
彼、ラタンに私は誠実な人柄を感じている。先日、ゆっくりとガンガー廻りをし、そろそろ帰ろうかと思う頃に姿を見せて、帰りの足の心配をなくしてくれた。
「映画に行こうかなー。今、何か面白いのをやってる?」と尋ねると、彼は胸を張り自慢げにきっぱりとこう言った。「もちろん。インドでは、一年中いつだって面白い映画を観られるんだよ」
そうだった。年間一千本も上映されるというこの国のことだ。行き先はラタンに任せて、私はリクシャーの座席に腰を下ろした。
夕食をホテルのレストランで取っていると、着飾った男女が次々とエレベーターに乗るのが目に入った。ボーイを捕まえて尋ねると、最上階のイベントホールで今晩結婚式があるのだと教えてくれた。
インドの結婚式! やったー。こんなチャンスは滅多にあるものではない。まさに千載一遇だ。私も出席させてもらおう。
すぐに部屋に駆け込むと、ここ一番という時のために持参していたお気に入りの浴衣に袖を通し、帯をきりりと締めた。
ホールの入口にガードマンが立って目を光らせていたが「ハロー」と笑顔で言うと、宿泊客と知ってか、あっさり通してくれた。
盛装した男女子供年配者で埋まった内部は、軽快なテンポの曲が流れ、立食パーティの最中だった。皆、取り皿にたっぷりと食べ物を載せ、スプーンと化した指で口に運んでいた。
会場のあちらこちらには、おめでたい時に使われるマリーゴールドのオレンジ色の花が華やかに飾られている。
カチッ、カチッ、とカメラのシャッターを切り続ける私の前に、でっぷりと太った白い民族衣装の初老の紳士が立ちはだかった。どうやら主催者らしい。
満面に笑みを浮かべ、両手を差し出して「ナイス ツー
ミーチュー コングラチュレイション アイム ウメキ フロム ジャパン」と恭しく挨拶をすると、彼は寛大にも、招待客のリストにはない遠来の客の飛び入りを瞬時に認めてくれた。そして、大皿を手ずから私に持たせ、見たこともない素晴しい料理の数々が並んだコーナーに導き、こう言った。
「さあ、今日はめでたい末娘の結婚式だ。なんでも好きなものを食べて、朝まで我々と一緒に祝ってくれ」
(5)
今朝も静寂を破るコーランの大音響で目覚めさせられた。ムスリムにモスクでの礼拝を呼びかけているのだが、世界中からヒンズー教徒が集まっているこの聖地で宗教騒動がよく起きないものだと感心してしまう。
カーテンを開けて外を眺めると、大通りを走る車の数は昼間に比べれば僅かだが、薄闇の中で人々はすでに一日を始めていた。
牛乳売りのリヤカー、その脇には道路を清掃する子どもたちも混じった家族の姿も見える。大八車で運んできた野菜を売ろうと荷を解く女や男たちの姿もある。
時計の針は五時を指していた。今朝はなぜか頭もシャンと冴えている。丁度いい。ガンガーの沐浴見物へ行こう。
大通りを渡り数分歩いたところで運転手のラタンの声がした、彼はこのところホテル横の空き地で夜を過ごしている。
「貴女は私の最高のお客さんだから、日本へ帰るまで専属のつもりでいるんだよ」と、噛み煙草で赤く染まった歯を見せながら言った言葉に違わず、いつ出てきてもすぐに出発できるよう待機してくれていた。
ガートに出るまで、あちこちに男たちが横たわっている。昨日の疲れがまだ取れないのだ。死んだようにピクリとも動かず、一様に白い足の裏を見せて睡眠をむさぼっていた。同じ場所に、同じように肉の垂れ下がった瘤牛や痩せた犬たちの姿もある。
東の空がゆっくりと白み、色のない河面に光が射し始めた。
待ちわびていた人々が動き出し、厳粛な面持ちでガンガーに身を浸し始めた。
様々な階層の人々も、何ヶ月もかけて地方から出かけてきた一団も、親の遺灰を流すためにやっとこの時を迎えた男性も、母なる大河に包まれて至福のときを満喫できるのだ。
彼らの深い信仰心をこの上なく崇高なものを見るように、異邦人の私は飽きることなく何時までも見入っていた。
(6)
帰国が明日に迫った。
ガンガーにさよならを言うため、ラタンのリクシャーに乗った。
彼は、食事にも、映画にも、ショッピングにも、少し遠出をするときにも、そして日課となったガンガーに行くときにも、いつも私の足とボディーガードになってくれた。
毎日顔を合わせていても、彼は決して客と運転手の関係を変えることはなかった。一緒に入ろうと映画にも食事にも誘ってみたが、感謝の言葉と共に丁重に断わられた。
インド映画は上映時間三時間はざらだが、彼は外で、私が戻って来るのをじっと待っていた。特に外国人観光客に対してしたたかな人々が多い中にあって、人間として培うべき誠実さを持った彼から私は多くのことを学ばせてもらった。彼に出会えて幸運だったと、心から思っている。
この日も、ガンガーは対岸がかすむほどの河幅を、悠々と、ほとんど流れている素振りすら見せず人々を優しく包み込んでいた。
ガートの石段にたむろする人の中に、現地人に同化したかのような服装の日本人の若者がぼんやりと河面を眺めている。近付いた私と視線が合った。こちらから声をかけてみた。
「どちらから?」
「大阪の……」
彼と私の住まいは偶然にも車で二、三十分という近距離にあった。大学は出たものの職につけず、将来が不安で、考えるのも嫌になってとりあえずインドに来てみたと、小声でぼそぼそと言った。
「大丈夫よ。人生は長い。貴方の未来は果てしなく広がっている。その健康な肉体と精神があれば、インドの子どもや大人や年寄りたちのように何だってやれる」
自分の息子に言うように彼を励ましたその時、この言葉は私自身を励ましていることに気がついた。
そうよ、人生は長い。まだまだこれから先三十年もある。ほんの少し白髪ができ、老眼鏡も必要になったけれど、唯それだけのことだ。その気になればまだ何だってできる。
これまでは家族だけに目を留めてきた。これからは外へ目を向けよう。さしあたって、インドへ発つ前に配布された広報誌に募集されていた、地域のボランティアに申し込みをしよう。私にもできることがあるかもしれない。なんでもいい、他の人の役に立ちたい。
それと、英会話の勉強も始めたい。単語を並べるだけでも通じはするが、もう少し上手く話せたなら、今回の旅だってもっと深くインドを知ることができたはずだから。
さあ、忙しくなってきたぞ。善は急げ、だ。帰国するとすぐに取りかかろう。
やる気と、新たな方向を得るきっかけを作ってくれたインドに感謝しながら、ごった返すホテルまでの見慣れた大通りをラタンのリクシャーに揺られている私は、もう前しか見ていなかった。 |
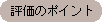 |
 |
| 筆者と同世代の女性の考え方、旅に対する思い、そして現地での交流の様子を素直に表現している。 |
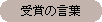 |
 |
結婚と同時に家庭に入り、家事と育児で月日が流れ、気づくと白髪と老眼鏡の五十路。今までの生きかたを変える時期がきたのだが、さりとてこれからは何を生き甲斐とすることができるのだろう? 答え探しの旅に選んだ先は、一度ツアーで行ったことのあるインドの、聖地ガンジス河とした。
この地で出会った老若男女の生き様と、大学は出たもののこれといった就職先が決まらずもがいていた日本人の若者との出会いから、やる気と新たな方向を見出すことができた。
旅の醍醐味は自分自身に対峙できること。調子良く行っている時も、落ち込んだ時も、私はいつも旅に出る。そこから力を得、再び進んで行くために、私はこれからも旅をする。
梅木 加津枝 |
|
 |
 |
 |

|

